「過去の病気」ではなく、今なお施設を脅かす感染症となります。
結核と聞くと、「昔の病気」と思われがちかもしれません。
しかし日本では、今も年間10,000人以上が新たに発症しており、特に高齢者の発症率は群を抜いて高いのが現実です。
しかも、結核は空気感染する感染症。
高齢者施設という閉鎖空間・集団生活の場では、一人の発症がクラスターの引き金にもなり得るのです。
適切な知識と対応があれば、恐る感染症ではありません。
これから、注意すべきポイントなどを解説させて頂きます。
目次
高齢者の結核は「再活性化型」が多い
高齢者の結核は、若い頃に感染していた菌が年齢とともに免疫力が落ちたことをきっかけに再発するケースが大半です。
症状がない状態を潜在性結核感染症(LTBI)と呼びます。
見逃されやすい理由
・症状が軽い、または「風邪と区別しにくい」
・微熱・倦怠感・咳・食欲不振などが慢性的に出る
・体力が低下してから初めてレントゲンで発見されることも多い
注意すべきサインと初期対応
職員が注目すべき症状
・2週間以上続く咳や微熱
・明らかな体重減少
・寝汗・だるさ・食欲低下
・他の呼吸器疾患と区別がつかないが、「長引いている」と感じたら要注意
対応フロー(疑い時)
- 医師へ報告し、速やかに胸部レントゲンと喀痰検査を依頼
- 確定診断まで原則個室隔離し、接触者のリストを作成
- 職員はサージカルマスクかN95マスクを使用(特に発症初期は感染力が高い)
空気感染対策がカギ
結核菌は非常に小さく、咳・くしゃみによる空気中浮遊粒子で感染します。
そのため、手洗いや消毒だけでは不十分で、空気の遮断と換気が重要になります。
感染防止策
・可能であれば陰圧個室(低圧を保つ個室)または居室の窓を開けて24時間換気
・空気清浄機やサーキュレーターの導入
・感染者の部屋へ出入りする職員にはN95マスク・ガウン・手袋の着用
接触者調査と二次感染の予防
施設内で結核が判明した場合、保健所と連携し、接触者調査(スクリーニング検査)を実施する必要があります。
実施対象
- 同室者や隣室の入居者様、席が近かった入居者様
- 日常的にケアに関わっていた職員
- 入浴やリハビリなど、密接なサービスを提供していた外部スタッフも含む
ワクチンと予防の考え方
高齢者に対するBCGワクチン再接種は基本的に行いません(予防効果がない)
ただし、職員や若年の接触者には検査後の予防投薬(INH服用)が検討されることがあります。
情報開示と対応の透明性も信頼を守るカギ
結核発症者が出た場合、施設運営として重要なのは「感染を隠さない」ことです。
過度に恐れる必要はありませんが、家族や関係者に迅速かつ正確な説明を行うことで、施設への信頼を守ることができます。
まとめ:「気づく力」と「止める力」が施設を守る
結核は発見が遅れるほど、周囲への感染リスクが高まります。
高齢者特有のあいまいな症状にいかに早く気づき、的確に動けるか、
それが、命と施設の安全を守る分かれ道となるのです。

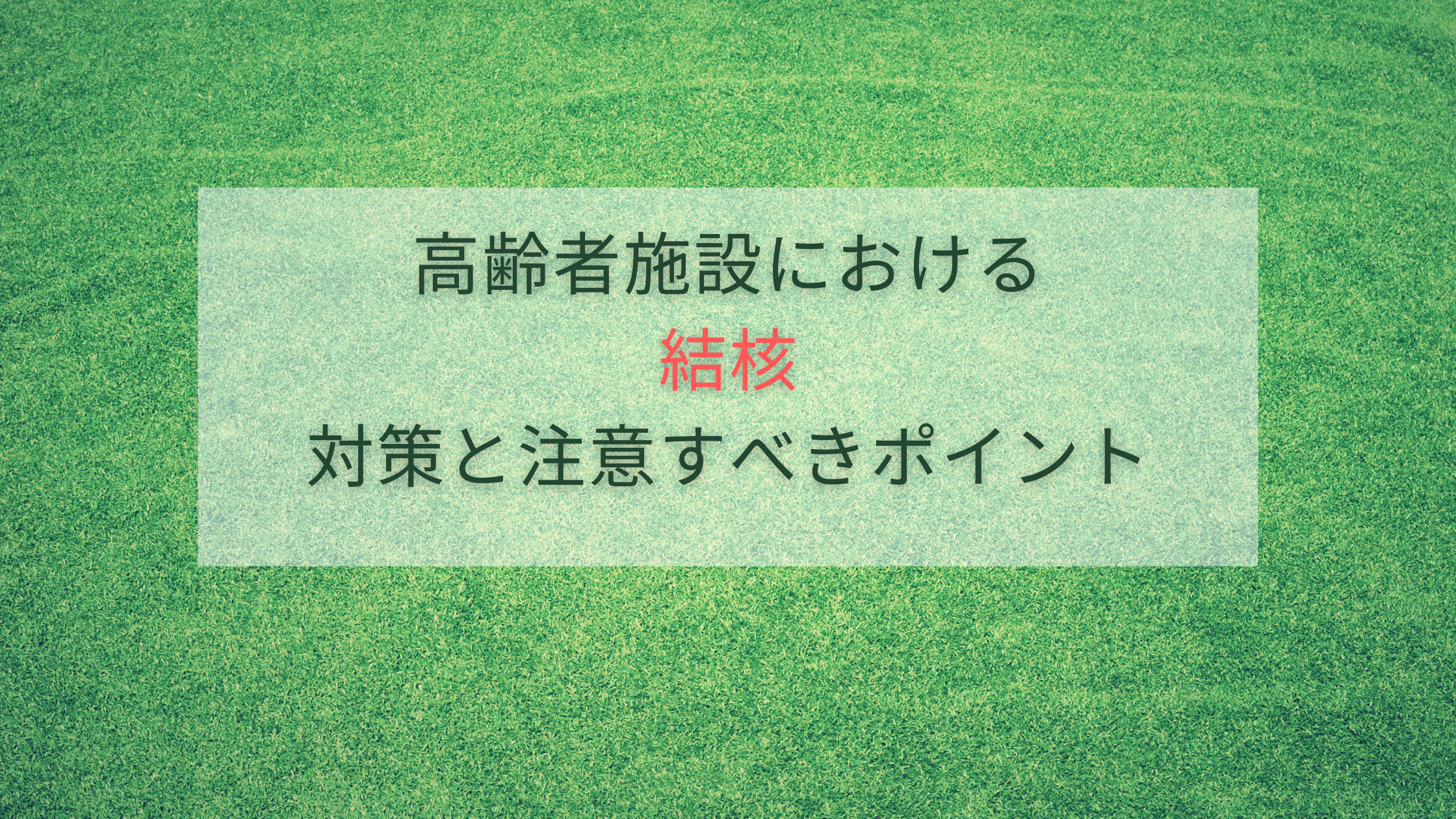

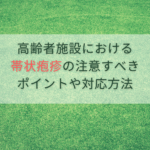
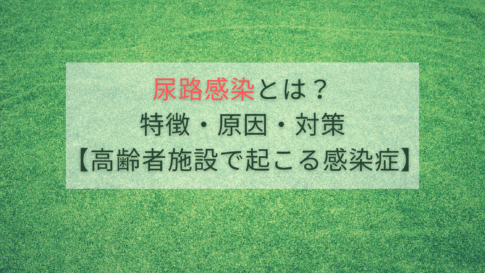
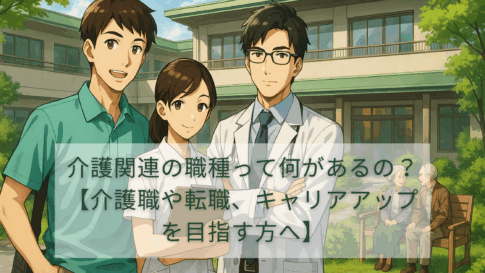



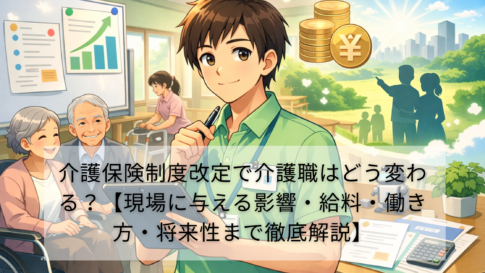




コメントを残す