”自律”と”自律”の違いをご存知ですか?
私たちの生活においても、この自立と自律は大切なものとなってきます。
私の培った経験などから、その違いを介護の視点でご説明させていただきます!
PR|介護の派遣をお探しなら!
目次
自立と自律の違いは?
ずばり
自立=自分でできること
自律=自分で意思決定できること
です。
例えば、
自立の例を挙げると
- 自分でご飯を食べれる
- 自分の足で歩くことができる
- 生活をすることができる
次に自律の例を挙げると
- 何を食べるのかを決める
- どこに行くのかを決める
- どういう暮らしを送りたいか決めることができる
このように、自律とは、「自身で決める」ことができる事を指します。
生活と暮らしの違い
自律に大きく関わる言葉として「暮らし」があります。
そこで、生活と暮らしの違いは何かを、今一度触れておきたいかと思います。
生活=生きるための営み(衣食住など)
暮らし=自分の想うままに生活する
つまり、生活と暮らしの違いは、そこに「想い(ニーズ)があるかどうか」です。
介護の基本は自律を目指すこと
介護での”じりつ”を目指すというと、多くの人が「自分でやる」「自分でできる」「リハビリ」などを思い浮かべるかもしれません。
もちろん、それも大切なことの一つです。
しかし、ここでいう”自律”というものは「自分で全てできるようになる」ことではありません。
本人が「望む暮らしを送れる」ように支援します。
例えば、
「食後は誰かと談笑したい」
⇒「しかし、すぐに入れ歯を洗浄するように促された」
⇒入れ歯洗浄に時間を取られて、友達と談笑できなかった
この場合は、入れ歯の洗浄を介護者が代わりにすれば、ご本人は友達談笑できたかもしれません。
このように、何でも自分で行う=”じりつ”ではありません。
あくまで、本人の意思決定のもとに行う”じりつ”である必要があります。
「機会費用」という言葉をご存知ですか?
これは、「Aをしなければ、Bができた」という、機会にかかる費用や時間のことを指します。
上記の例でいうと、「A:入れ歯」と「B:友達の談笑」が機会費用ということになります。
自律を目指すには?
では、”自律”を目指した支援をするにはどうしたら良いのでしょうか?
1. 良く観察する
最も重要なのは、「できないこと」ではなく「できること」に目を向ける観察力です。
ご本人からの言葉はもちろん、ほんのわずかな動作、自分から動こうとする意志、日々の変化に敏感になることで、ご本人が本来持っている力や可能性が見えてきます。
その力を信じることが、自律支援の第一歩です。
2. 手伝う”前に”考える
介護の現場では、つい「お手伝いした方が早い」と感じることも多いものです。しかし、自律を促す介護では“あえて待つ”ことも必要です。時間がかかっても本人にやってもらう。失敗してもやり直せる環境をつくる。その余白が、自立心を育てる土壌になります。
前項で話した「代わりに行う」と相反するようですが、あくまで、本人の意思が重要となります。
3. 環境を整える
自分の力でできるように促すには、適切な環境づくりが不可欠です。
たとえば手すりの設置、衣類の工夫、生活動線の見直しなど、ほんの少しの工夫で「できること」は格段に増えます。環境を“操作する”のではなく、“整える”意識が重要です。
4. 心に寄り添ったコミュニケーション
自律を目指すうえで欠かせないのが、本人の「やりたい」という気持ち。支援者は、本人の希望や価値観に耳を傾け、その人が「自分の人生をどう生きたいか」を尊重する姿勢が求められます。一方的な指導や命令ではなく、“対話”によって、行動のモチベーションを引き出していくことが重要です。
5. 支援者自身の価値観を見直す
ときに、支援者の中にある「こうあるべき」「こうすれば楽」という思い込みが、相手の自律を妨げてしまうこともあります。支援とは相手の人生に寄り添うこと。そのためには、支援者自身が常に自分の価値観と向き合い、柔軟に対応する姿勢が求められます。
まとめ
高齢者や障がいを持つ方々が、自分の意思で暮らしを選択し、できることを自分の力で行う。
これは生きる尊厳を守ることに直結しています。
「やってあげる介護」ではなく、「できるように導く介護」こそが、その人の人生をより豊かにします。
自律支援の介護では、「できること」と「できないこと」を丁寧に見極める視点が求められます。必要な部分だけをサポートする。ほんの小さな行動であっても、それが本人にとっての“できた”という実感につながり、自信を取り戻すきっかけになります。
介護の現場では、目の前の困りごとを解決することに追われがちですが、一歩立ち止まって考えてみてください。
“この方は本当は、どこまで自分でできるのか”
”どういう暮らしを送りたいのか”
その問いを忘れずに支援を続けていくことが、結果的に本人の生活の質を高め、介護する側の負担も軽減していくことにつながります。
介護のゴールは「守ること」ではなく、「自分らしく生きる力を取り戻してもらうこと」
その道しるべとして、「自律を目指す介護」という視点を、ぜひ日々のケアの中で意識してみてください。

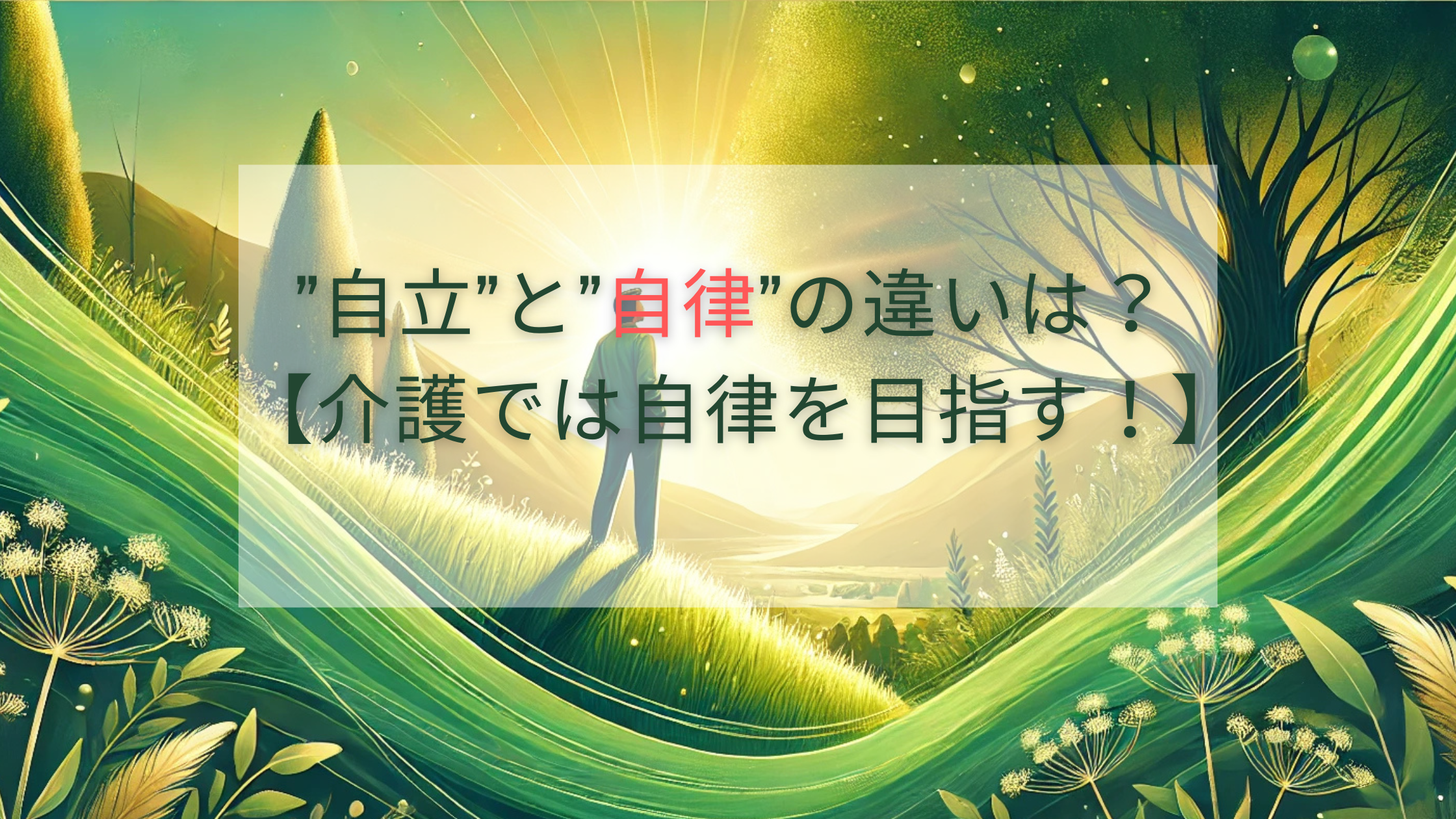
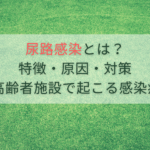
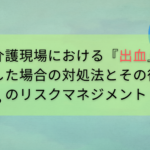
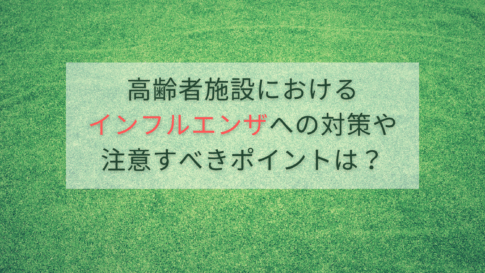
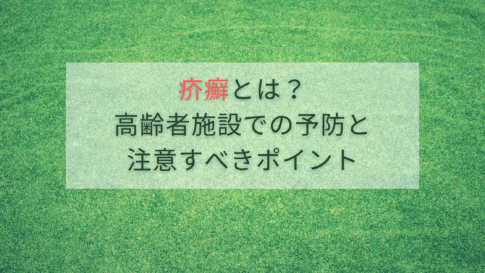


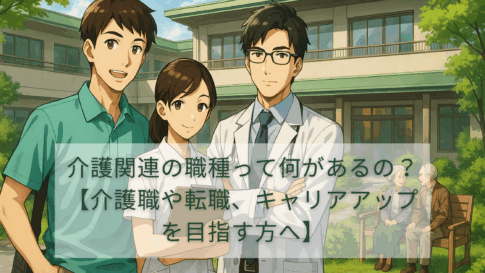
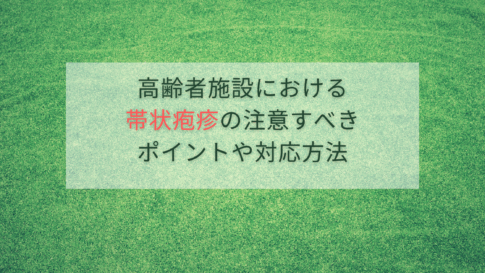
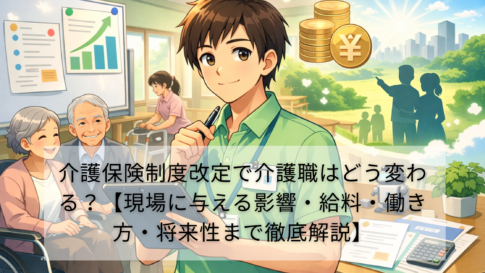
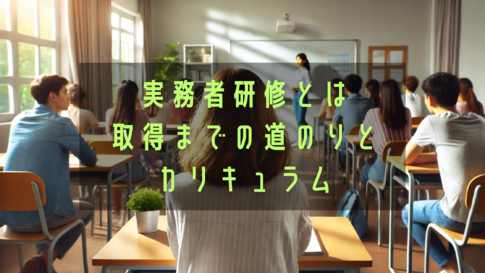



自律を実現するには、暮らしの実現も同時に考える必要があるんですね!