「発疹と痛み」は、帯状疱疹のサインかもしれません。
高齢者の肌に突然現れる赤い発疹と強い痛み。それは帯状疱疹の始まりかもしれません。
この疾患は、水ぼうそうウイルスの再活性化によって起こる皮膚と神経の病気であり、
高齢者施設では特に注意すべき感染症のひとつです。
発症の早期発見と、感染拡大の防止対応が何よりも重要です。
目次
帯状疱疹とは?
帯状疱疹は、過去に“水ぼうそう”にかかった人の体内に残っていた「水痘・帯状疱疹ウイルス」が、免疫力の低下をきっかけに再び活性化して起こる病気です。
高齢者は免疫機能が落ちやすいため、発症率・重症化率がともに高い傾向があります。
特に注意したい症状と見極めポイント
・身体の左右どちらか片側に帯状の赤い発疹・水ぶくれ
・皮膚のピリピリした痛み(皮膚症状より先に出ることも)
・顔・頭・胸・背中・腹部・腕・足などどこでも発症する可能性あり
・「なんとなくヒリヒリする」
・「衣類が当たって痛い」
・痛みだけで発疹がまだ出ていない場合も要注意
高齢者施設での対応方法 〜感染対策とケアの両立〜
1. 発見したら看護師に報告
・看護師に報告し、指示を仰ぎます
・速やかに医師の診断を受ける(抗ウイルス薬は発症72時間以内が効果的)
・診断が出たら、感染経路と重症度に応じてゾーニングを検討
2. 感染予防の基本は「接触・飛沫」の遮断
帯状疱疹は空気感染はしないものの、水ぶくれに含まれるウイルスが接触感染や飛沫感染を引き起こします。
特に、支援中に水ぶくれが割れたりしたら要注意です。
・水疱が破れている場合は感染力が高い
・水疱がかさぶたになるまでは職員は手袋・マスク着用で対応
・他の入居者との入浴・食事の同席を控える
入浴支援に関しては、一時的に清拭や更衣のみを検討する必要もあります。
また、帯状疱疹による痛みも考慮する必要があります。
3. 施設内での感染拡大を防ぐためのゾーニング
基本、接触感染を遮断することが効果的です。
それを踏まえてゾーニングする必要があります。
・個室隔離または仕切りを設けた専用エリアに移動
・居室内のリネン・タオル類は専用で管理・洗濯
・接触した物品(椅子・寝具など)は毎回消毒
4. 職員・家族への情報共有とワクチンの検討
帯状疱疹は、水ぼうそうにかかったことがない人に感染する可能性があります。
特に妊婦や小児への二次感染リスクも踏まえ、情報共有は慎重かつ迅速に行う必要があります。
・発症者が出た場合は職員へ共有し、感染予防意識を強化
・職員や入居者へのワクチン接種(シングリックスなど)の検討も有効
後遺症「帯状疱疹後神経痛」にも配慮する
発疹が治っても、ピリピリとした痛みが長期間続く「帯状疱疹後神経痛(PHN)」になるケースがあります。
これは高齢者に多く見られ、生活の質(QOL)を著しく下げる要因です。
・痛みによる不眠・食欲低下に注意
・医師の処方による鎮痛薬やリハビリ指導の活用
・「治ったように見えても痛みが続く」ことを職員全体で共有
まとめ:帯状疱疹は「発見の速さ」がすべてを左右する
帯状疱疹は、早期に気づいて正しく対応すれば、大きな感染拡大を防ぐことができます。
しかし、皮膚トラブルと見誤る・痛みだけで終わると思って放置する。
こうした見逃しがリスクを高めます。
「なんとなくの痛みや違和感」を見逃さず、「早めの受診・的確な対応・感染予防の徹底」が、施設の安心・安全を守る力となるのです。

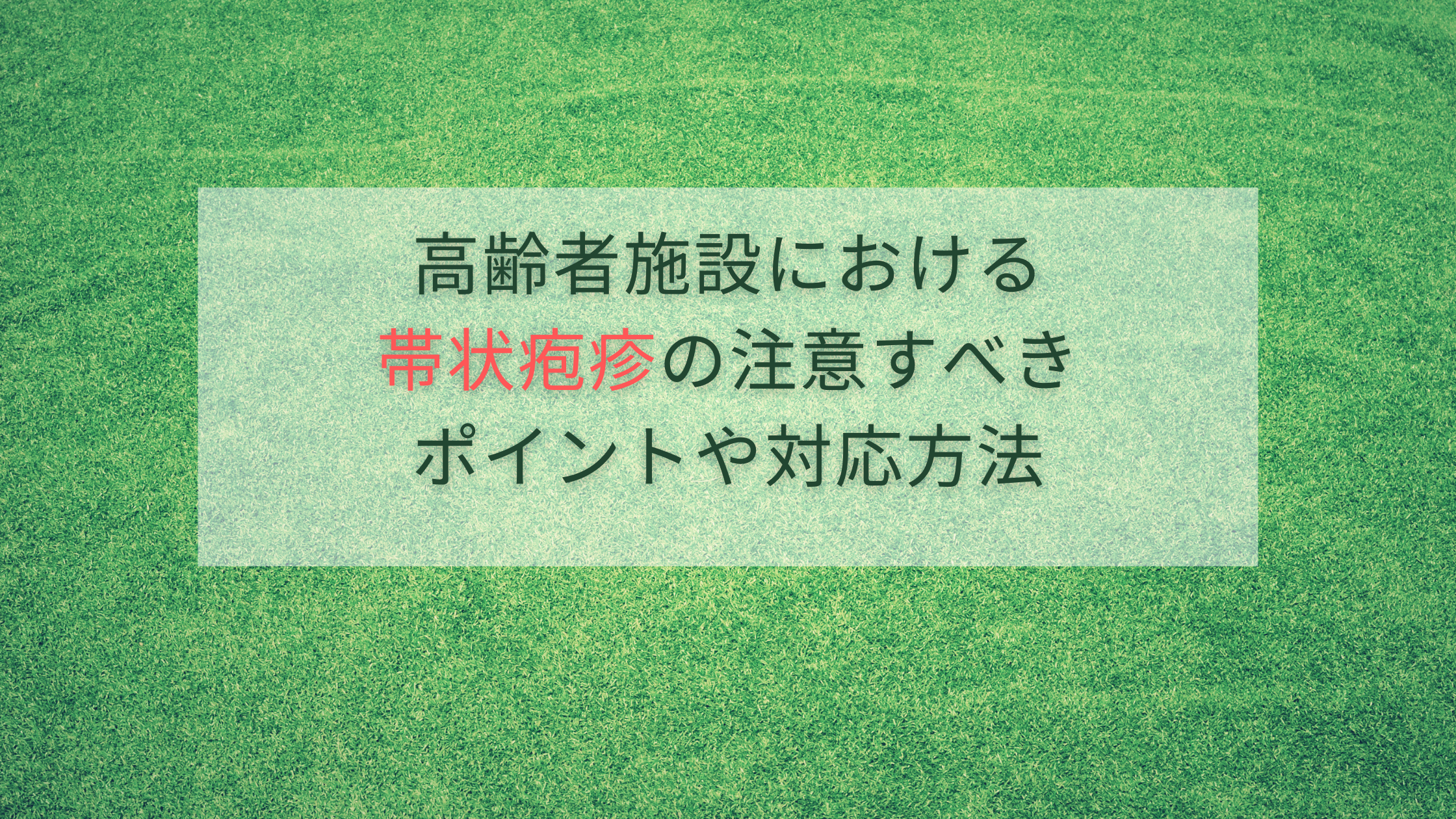
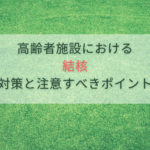
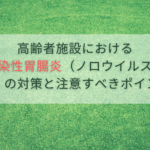

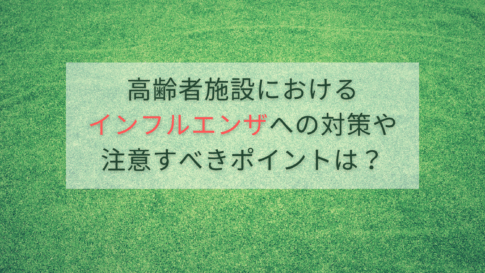



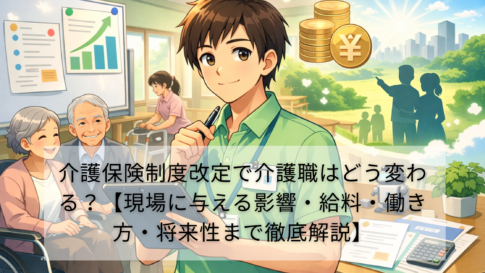
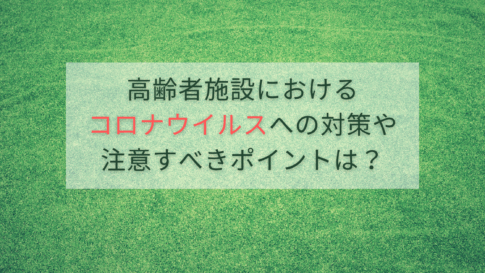
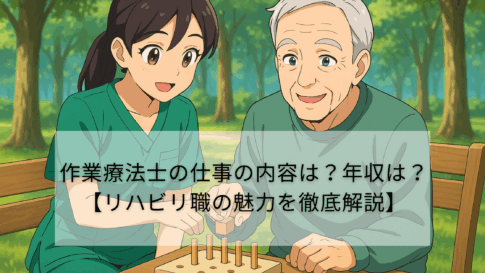



・皮膚の異常や痛みを見逃さない
・過去に水ぼうそうにかかったことがない職員等は極力支援に入らない
・水疱が割れると感染力が強くなる