こんにちは!レナードです(@レナード)

確かにそうですね。
しかし、介護過程では、アセスメント〜経過を見ていくまで、介護職員が行います。ですから、しっかりと介護過程を学ぶ必要があるんですね。
介護過程では、ご利用者様を中心に、ケアマネ・看護師・相談員・・・そして介護職員。
全ての方が携わります。
その中でも、介護職員は、実際に支援内容を実行し、ご利用者様のニーズを間近で聞くポジションです。
ですから、介護職員は、介護過程の中核を担います。
これから、その介護過程の基礎を解説していきます!
目次
介護過程とは
介護過程とは、ご利用者様の望む生活を実現するため、生活課題の発見・計画・実践・評価をしていく一連のプロセスです。
介護過程の流れ
それでは、介護過程の流れを解説していきます。
アセスメント(情報収集・情報の統合化)
アセスメントとは、対象ご利用者様の情報収集・分析・統合をし、課題発見のための材料集めです。
情報収集
情報収集では、項目ごとに「できる事」「支援が必要なこと」「ニーズ」この3つに分けて考えると、情報が整理しやすいです。
情報収集は特に大事です。
ここの情報収集がきちんとできていないと、後述する関連付けや、それ以降のプロセスに大きな影響を及ぼします。
情報収集フォーマットの参考として以下に、私が作った表を添付します。
| 項目 | 入居者の状況 | 援助内容 | ニーズ | |
| ADL状況 | 移動 | |||
| 食事 | ||||
| 入浴 | ||||
| 更衣 | ||||
| 整容 | ||||
| 意思疎通 | ||||
| 精神状況 | 睡眠 | |||
| 認知症・その他 | ||||
| 社会性 | 外出 | |||
| 他入居者との交流 | ||||
| 家族との交流 | ||||
| 行事参加 | ||||
| 地域との交流 | ||||
分析・解釈・関連付け・統合化
情報収集で集めた情報をもとに分析します。
分析には、解釈と関連付けが含まれます。
ここでの解釈とは、ニーズがご利用者様の今の状態とマッチしていない個所を見つけ出し、その原因を探ります。
そして、複数の箇所を見つけたら、相互に関連しないか関連付けをしてみます。
例えば、「入居者の状況AとBは、ニーズAと関連しそうだな」と思ったら、関連付けて考えてみます。
例えば、夜間不眠のご利用者様は、日中の活動量や意欲などと深い関係があります。これらを関連付けて考えることで、広い視野で分析することができます。
この関連付け次第でアプローチ方法が異なります。
上記の例の夜間不眠であれば、例えば
A「夜間不眠は睡眠環境の問題がある⇒証明・音・寝具などの見直し」
B「夜間不眠は日中の活動量に問題がある⇒日中のレクや役割を増やしてみよう」
など、関連付ける情報によっては、取り組み内容が異なり、ここできちんと関連付けができていないと、効果がない取り組みを行ってしまうことに繋がります。
課題・ニーズの決定
アセスメントが終わったら、それを課題やニーズとして起こします(文章にする)。
書き方の型としては
・ニーズと現実のギャップ
・そのギャップが継続されるとどうなるのか
・原因
・必要な支援は何か
という4つのステップで書くと書きやすいです。
長期・短期目標の決定
1つの課題に対して、長期目標と短期目標を設定します。
長期目標と短期目標は、ご利用者様視点で書きます。
例えば「〇〇できるようになる」「〇〇したい」など
長期目標は、6カ月間など、長期の視点で達成したい目標を設定します。
この長期目標は、課題解決に直結する目標となります。
一方短期目標は、長期目標を達成するための小目標です。
例えば、長期目標が「トイレの自立が継続できる」たとすれば、短期目標はそれを達成するためには何をしたらいいのかを書きます。
例えば「毎日立ち上がり運動をする」や「トイレの場所を把握できる環境でサービスを受けられる」の様に書きます。
考え方のコツは、課題⇒長期⇒短期で左から順に分解して考えることです。
支援内容の決定
ここでは、短期目標それぞれの支援内容(中身)を書きます。
つまり、短期目標を達成するための具体的な実施内容を書きます。
ここでは、できる限り、回数やタイミングなども踏まえ具体的に書きます。
我々介護福祉士は、この支援内容をもとに支援を実施していきます。
その為、ここが具体的でないと実施できなくなります。
立案
立案は上記までの課題(ニーズ)・長期目標・短期目標・支援内容を記載します。
プラスで、期間と誰が行うか(介護職員なのか、看護師なのかなど)を明記します。
経過
立案し、支援をしたら経過を記録しましょう。
ー経過を書く際のポイントー
・支援内容を実行したみたご利用者様の反応(表情や言動など)
・意欲(言動など)や身体状況の変化(できる事が増えた、など)
・課題に対する変化(例えば、「リビングまで歩行できる」が目標だとすれば、現段階で「どこまで歩行できたか」など)
評価
立案する前月に行います。(立案をしてから5ヶ月後)
経過情報から、短期目標・長期目標が達成できたか・できなかったか。を記載します。
ここでポイントですが、まずは達成したか、していないかを見極めます。
そのあとで、なぜ達成できなかったのか(原因)を考えます。
基本的には、短期目標が達成できていないと、長期目標も達成できたとは言えません。
もし、短期が達成できていないのに、長期が達成できたと感じる場合は、「短期目標の設定が間違っていた」か「評価の方法に問題がある」事がほとんどだと思います。
1つずつ評価し終えた後は、次回(来月)の立案に向けて、再アセスメントや課題の目星をつけておきましょう。
基本は、立案(1ヶ月)・経過(4ヶ月)・評価(1ヶ月)の6ヶ月周期で行います。
介護過程の注意点
介護過程の注意点としては以下が挙げられます。
- ご利用者様及びご家族様に報告・許可を得る
- プライバシーの配慮に注意する
- 職員目線ではなく、あくまでご利用者目線
- 介護過程次第で、ご利用者様の人生が変わることを念頭におく
我々、介護福祉士は本物のケアプランを作成したりはしません。
間にケアマネージャーが入ります。
その為、実際にご利用者様の人生を左右する計画を立てるわけではないかもしれません。
しかし、一番身近にいる我々介護福祉士は、ご利用者様のことを一番よく分かっています。
その我々が、作った介護過程や経過情報には信憑性があります。
ですから、間接的に・・・いや、直接的に、ご利用者様の人生を左右することは間違いありません。
なので、この介護過程というプロセスは極めて重要なのです。
介護過程のコツ
介護過程のコツとしては以下が挙げられます。
- 情報収集を念入りにしっかり行う
- 課題抽出に迷ったら「移動・排泄・入浴・食事・移乗+精神」に目を向ける
- 紙に図を書いてみる
情報収集は、介護過程の入口にして、最も重要なプロセスです。
先述した通り、ここがしっかりできていないと、ニーズと支援内容がマッチしていないケアプランが作成される可能性があります。
自立していればしているほど、課題抽出が迷ったりますよね・・・。
そんな時こそ、ふわっと考えるのではなく、5大介護+精神に目を向けると課題が見つかりやすくなります。
それでも、課題抽出が苦手だという方は、紙に相関図などを適当でもいいので書いてみましょう!
書いて思考が整理されることはよくあります。
なぜ、課題抽出ばかりに目を向けるのか。
それは、課題抽出さえできてしまえば、あとはそれを達成するための長期目標・短期目標・支援内容を考えるだけだからです。
まとめ
おさらいです。介護過程の流れは
- アセスメント(情報収集・分析・関連付け・統合化)
- 課題・ニーズ抽出
- 長期目標・短期目標・支援内容を決定
- 期間・誰が行うかを決定
- 経過を見ていく(きちんと記録していく)
- 評価
- 立案
です。これを6ヶ月周期で繰り返します。
ケアプランは、ご利用者様の人生を左右するかもしれないとっても大事なことです。
我々介護福祉士(介護職員)は、その中の中核を担う存在です。
介護過程を成功させ、ご利用者様により良い暮らしを提供できるように日々私も勉強していきます!




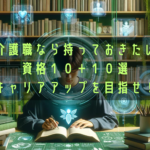



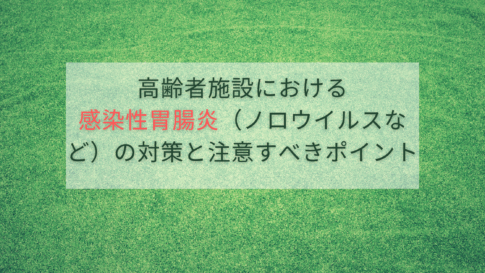
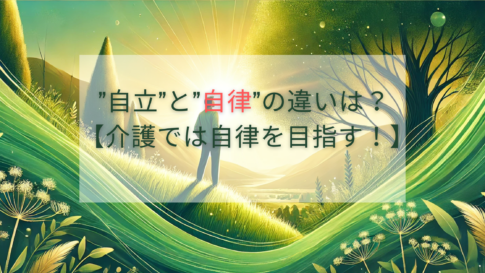
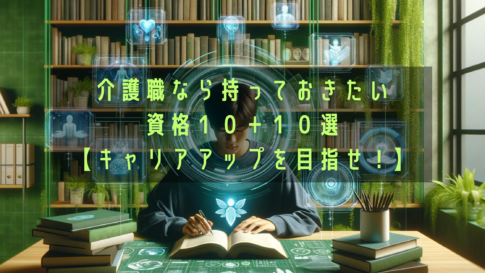




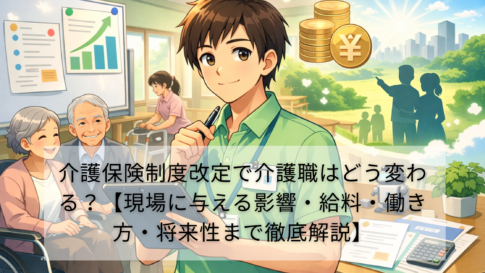

ケアプランはケアマネが作るんでしょ?