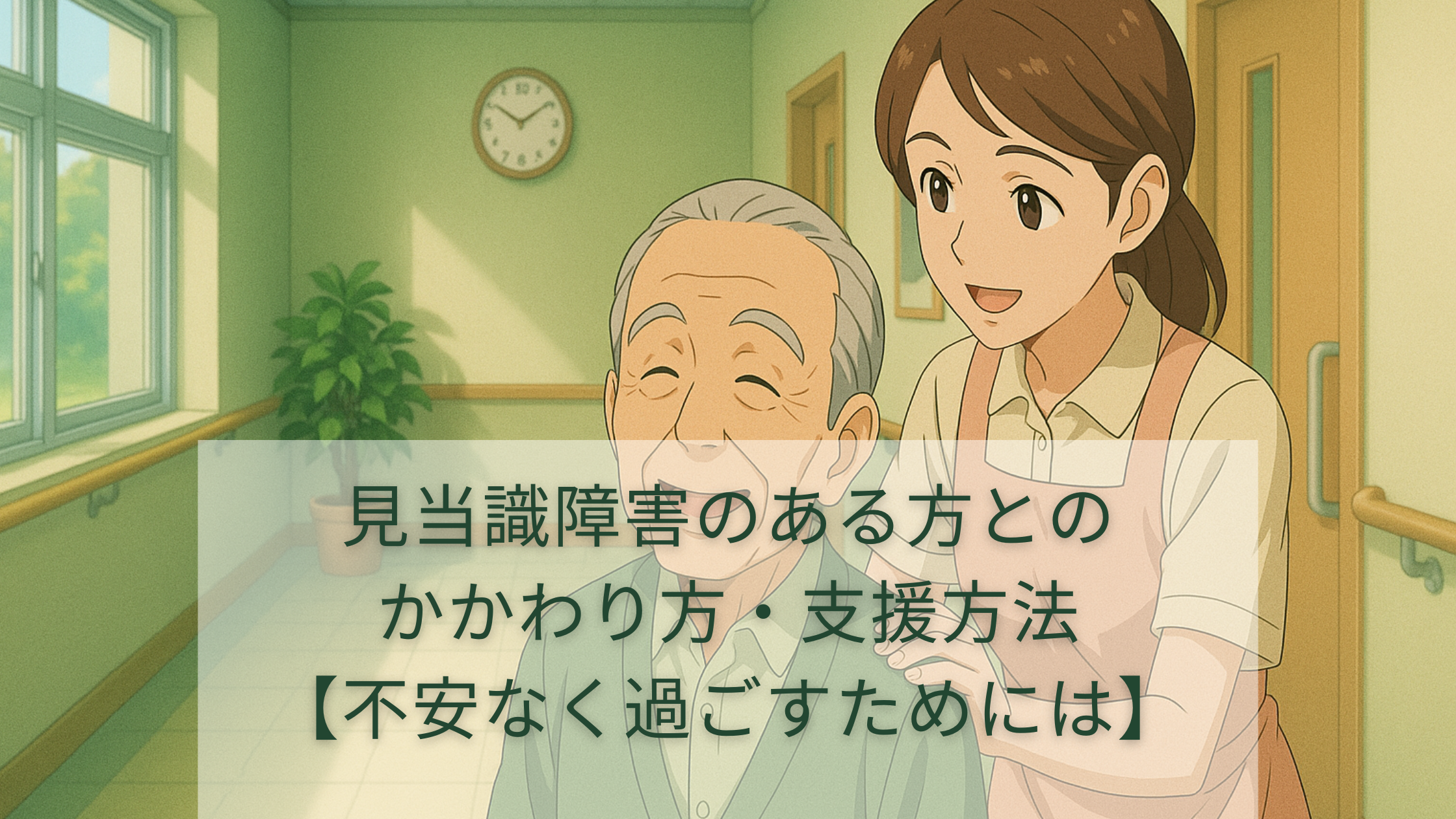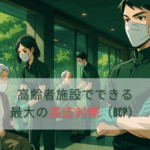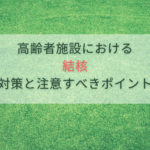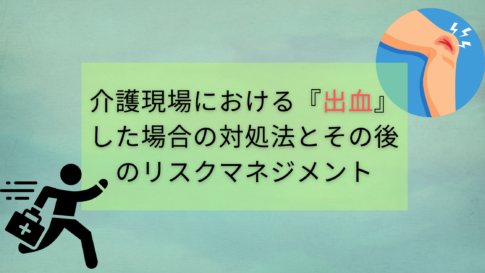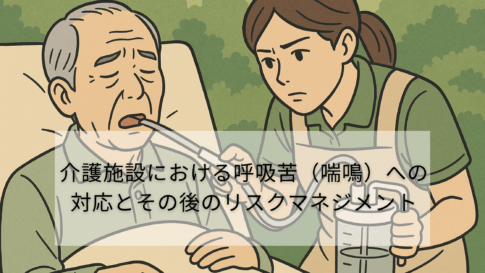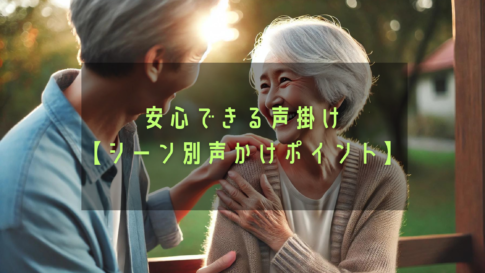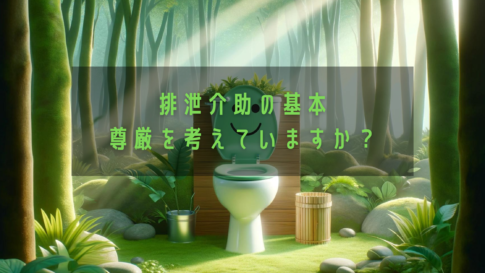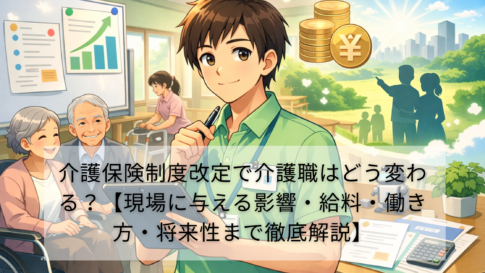「ここがどこかわからない」
「今は何時だ」「そんなはずはない」
などの、場所と時間がわからないご利用者様の支援で困っていませんか?
それはズバリ、見当識障害というものです。
この記事では、見当識障害についての基礎知識や考え方、支援方法をご紹介させて頂きます。
- 見当識障害とは
- 見当識障害がある方との関わり方、支援方法
目次
見当識障害とは?
見当識障害とは
見当識障害とは、
自分が「いつ」「どこに」「誰と」いるのかといった認識(=見当識)がうまく働かなくなる状態を指します。
人が日常生活を送るうえで大切な基盤となるのが「見当識」です。
これが障害されると、時間や場所、人との関係がわからなくなり、不安や混乱、行動の困難さにつながります。
見当識の種類
見当識は段階的に働いており、以下のように障害される順番もおおむね決まっています。
- 時間の見当識:今日は何年・何月・何日か、朝か夜か。
- 場所の見当識:ここがどこなのか、自宅か病院かなど。
- 人物の見当識:目の前の人が誰なのか、家族なのか他人なのか。
今がどの段階(障害)にあるかを見極めることも重要です。
見当識障害が起きやすい原因
- 認知症(特にアルツハイマー型認知症)
- 脳卒中や頭部外傷などによる脳の損傷
- 精神疾患
- 発熱や感染症、薬の副作用などによる一時的な意識障害
主に認知症の方に多く、初期段階から見られることがあります。
見当識障害のある方との関わり方で大事なことが、まずは見当識を理解することです!
見当識障害がある方との関わり方の基本
まずは受け止めて、安心できる声掛けをする
見当識障害のある方にとって、世界は予測できない出来事の連続です。
そのため、介護者が否定的な対応をしてしまうと、不安や怒りが一気に高まります。
たとえば、本人が「家に帰る」と言ったときに、
「ここは家じゃありませんよ!」と正論で返すと、混乱が強まりやすくなります。
本人にとっては、「ここは家」という事実だからです。
⇒ポイントは「否定しない」「安心できる言葉を添える」こと。
例えば
「今日はもう暗くなってきましたね。少し休んでからにしましょうか。」
このように気持ちに寄り添いながら、行動を穏やかに切り替える声かけが効果的です。
何が分からないのか見極める
見当識障害のある方は、不安が強まると落ち着きがなくなる、同じ質問を繰り返す、表情が険しくなるなどのサインを見せます。
こうした初期サインを見逃さず、何が分からないのかを把握するようにします。
そうすることで、適切な声掛けや環境を整える材料になります。
信頼関係を作る
普段から信頼関係を作ることも大切です。
誰に話を聞いてもらうか、声を掛けられるかも大事な要素となります。
本人に合わせた環境を整える
見当識障害の初期には、時間や場所を示す情報を環境に取り入れることで、不安を軽減できます。
- 大きな文字のカレンダーや時計を見やすい位置に設置
- 朝・昼・夜のメリハリがつく照明やカーテンの活用
- 部屋や廊下に「トイレ」「食堂」などの案内表示を設置
これらは、本人が自分で状況を確認できる「安心材料」になります。
また、日課を一定に保つことで、「次に何が起こるか」を予測できる安心感も生まれます。
⇒自分でできる事を見つけていく支援も大切です。
安心できる毎日を
見当識障害のある方との関わり方で大事なのが、
その障害・症状を理解して寄り添う事です。
誰でも、「ここ〇〇に違いない」や「ここはどこで、今はいつだ」と思っているときに、闇雲に「違いますよ」などと言われたら、不安になると思います。
まずはそのことを理解することが大事です!
適切な声掛け、環境を構築し、その方にとって安心して暮らせることがその方のQOLに大きく関わります。