目次
食事介助の意義
- 健康維持と栄養管理
適切に栄養摂取をサポートすることで、ご利用者様の健康状態を維持し、意欲向上・病気の予防、回復を促進します。 - 自尊心の維持
日常生活の一部だからこそ、出来ること・できない事を見極めて介助し自力をサポートします。 - 嚥下障害の予防と改善
口腔摂取の機会が減ると、咀嚼能力・嚥下機能が低下していきます。日々の口腔摂取をサポートする事で、口腔内の能力を維持・向上させていきます。 - 社会的な繋がりの維持
食事はコミュニケーションの場でもあります。介助者や他のご利用者様と一緒に食事をすると社会的なつながりを感じることができ、孤独感を和らげることができます。 - 生活の質(QOL)の向上
食事は日常生活の中で重要な楽しみの1つであり、これをサポートする事は全体的な満足感を高めます。
食事介助の流れ
- 準備
・ご利用様の状態確認(体調や気分、嚥下状態)を確認します。
・環境の確認(椅子やテーブルの高さ、衛生面、危険なものはないか等)
・介助者及びご利用様の手洗い(流水で手を洗い、手指消毒)
・ご利用者様の姿勢の確認(深く座っているか、斜めっていないか等) - 声かけ
時間とご飯である事を伝えます。また、この時にメニューをお伝えしましょう。 - 介助
・まずは水分を勧めましょう。
・何を食べたいか伺いながら介助します。希望が聞くことができない場合は、ご飯・主菜・副菜とバランスよく介助します。
・その方にあった一口を意識しながら介助します。
・飲み込み確認をしっかりしてから、次を運びます(喉仏の動きや、口元の動きで判断します。)
・随時、声をかけながら介助していきます。
・随時、水分を勧めましょう(3〜5口に1回程度) - 食後
・口腔内の残渣物確認。口腔内に食べ物が残っていると誤嚥のリスクが高まります。
・食後は口腔ケアをしましょう。
食事介助の注意点
誤嚥
食事介助で最も注意しなければならないのは「誤嚥」です。
誤嚥を防ぐポイントとしては
- その人にあった食事形態・水分形態にする
食事形態であれば「常食」「一口大」「特刻み」「ミキサー」などがあります。
水分では、とろみ剤を用いてとろみをつけます。 - ごろつきや軽いむせ込みはないか
軽くむせ込んでいる時点で軽い誤嚥ですが、この時点で無理せず中止することがポイントです。大きな誤嚥に繋がります。 - 嚥下・咀嚼機能の把握と周知
関わりが多い介護士であれば状態を把握していることでしょう。しかし、新人や時々関わる介護士は嚥下・咀嚼機能の把握が十分ではないことがあります。誤嚥事故を起こす可能性が高いのが、情報把握不足だったりします。ですから、しっかりと情報を周知することが必要です。 - 姿勢の確認
顔が上向きや下向きの場合は、誤嚥しやすくなります。また、座位姿勢も、浅く座っていたりすると顔が上向きになってしまったりなど、体全体の姿勢バランスも注意して観察する必要があります。 - 適切な一口量
一人ひとり、適切な一口量が違います。その為、最初のうちはスプーンの2分の1ぐらいから運び、徐々に増やしていくやり方がおすすめです。多くても、スプーンに小さな山ができるくらいでしょうか。 - きちんと飲み込み確認をする
誤嚥事故が起こりやすい状況の1つとして「ペースが早い」ということが挙げられます。少しでも口腔内に残っていたり、次から次へと飲み込むペースが早いと、落ち着いて飲み込めず誤嚥を誘発します。
できるだけ足を床につける
できれば車椅子ではなく、高さに合った椅子に座っていただき、床に足をつけていただく方が良いでしょう。
足が床につくことで踏ん張りが効き、咀嚼力が20%程アップすると言われています。
コミュニケーション
どの支援でも大切なことですが、コミュニケーションを図りながら少しずつ信頼関係を構築していきます。
知らない人に介助は誰もされたくはありません。
また、趣味趣向などの情報収集や、楽しい空間を演出できる効果もあります。
食事介助で起こりやすい事故
誤嚥・窒息
注意点の所でも話をさせて頂きましたが、気管に異物(飲食物等)が誤って入ってしまう誤嚥(重度なむせ込み)は食事介助と隣り合わせに会える事故の代表格です。
高齢者の方は、気管支が弱くなっていおり、また、食事介助=自分のペースで食べることが難しい場合は特に誤嚥しやすい状態となっていると言えます。
誤嚥の最も重度なものが窒息です。
窒息は、命の危険に直結します。
窒息すると、3~5分で顔色が悪くなり、5~6分で呼吸が止まります。そのため、5分で回復させることが対応の目標と言われています。
さらに15分を過ぎる脳死状態になるとされています。
誤嚥性肺炎
誤嚥から回復してもまだ油断はできません。
誤嚥性肺炎が待ち受けている可能性があるかです。
誤嚥性肺炎とは、誤嚥により異物が肺に侵入することで炎症を起こす病気です。
誤嚥性肺炎の特徴は、発熱とサチュレーションの低下です。
誤嚥から回復してしばらく(約1日~5日)は注意深く観察し、変調があればすぐに看護師に報告しましょう。
口腔内の怪我
使う食器や支援方法によっては、口腔内及びくちびる等を怪我してしまう可能性があります。
口腔内への食器運びの仕方、唇を必要以上に拭きすぎないように注意しましょう。
口腔内にスプーンを入れる時は、やや上から斜めに侵入し、上斜めに引くと負担が少なく済みます。
嘔吐
食事のペースが早かったり、量が多いと嘔吐の原因になります。
少しでも気持ち悪そうにしていたり、飲み込むペースが遅くなったら、無理せず休憩または中止しましょう。
アナフィラキシー(アレルギー反応)
事前にアレルギーは確認しておきましょう。
厨房から運ばれてくるタイプの施設でも、厨房の人がミスをするかもしれません。
そのため介護職員もきちんと把握し、チェックすることが大切です。
まとめ
食事は暮らしの中で重要な意味を持ちます。
栄養摂取はもちろん、
味で楽しむ
見て楽しむ
会話で楽しむ
など、生きがいの1つになっているかもしれません。
ですので、ぜひ、楽しみにある食事時間を提供したいものですね♪





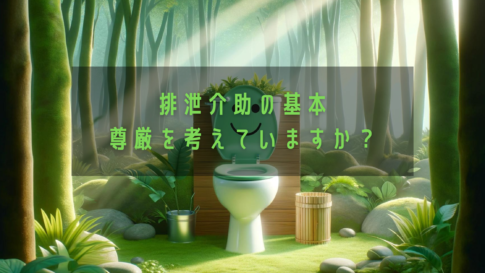
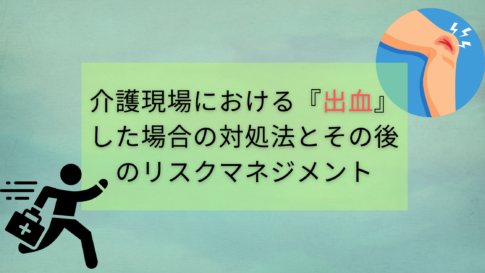

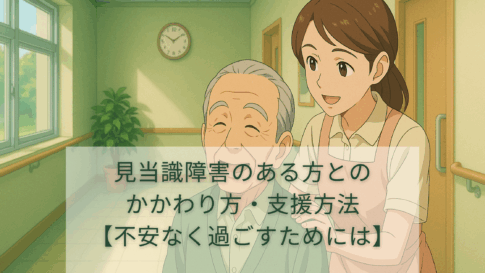
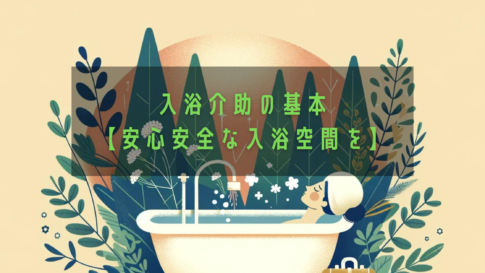

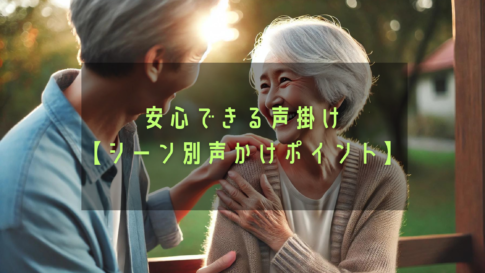


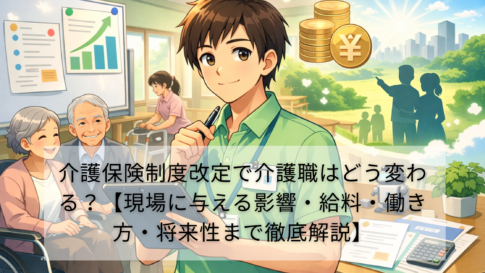

コメントを残す