出血した時、どう対処したらいいのか困った経験はありませんか?
看護師呼ぶにしても、まずは何をしたらいいのか・・・
ほっとくわけにはいかないし・・・
それに、看護師がいる時間はいいですが、夜間在住していない施設も多くあります。
その場合、看護師が駆けつけるまでに時間がかかります。
とりあえず応急処置をしないといけません。
そして、大事なのは、出血後の分析と改善行動です!
その術をこの記事では解説させて頂きます!
目次
どんな時に出血する?
介護現場で働いている方であれば、出血する原因は思いつくかと思います。
それでは、今一度確認しておきましょう!
《出血する要因》
- 皮膚のもろさによる出血
・加齢に伴い皮膚が薄くなり、ちょっとした刺激で出血しやすくなります。例えば、ベッド柵やトイレットペーパーホルダーのギザギザ、車椅子のフット・アームサポートなどに引っ掛けてもすぐに出血する場合があります。
・毛細血管がもろくなり、軽い打撲や摩擦で内出血や皮下出血(あざ)ができやすい。 - 外傷による出血
・高齢者はバランスを崩しやすく、転倒や転落による出血が多い(頭部、手足、顔など)。
・ 料理中の包丁や、紙や爪による軽い切り傷でも出血しやすい。 - 服用している薬の影響
・抗凝固薬(ワルファリン・アスピリンなど)の血液をサラサラにする薬を服用していると、少しの傷でも血が止まりにくくなる。
・ステロイドの長期使用により 皮膚が薄くなり、出血しやすくなる。 - 病気による出血
高血圧:血管に負担がかかり、脳出血や鼻血の原因になる。
糖尿病:血管がもろくなり、目(網膜出血)、皮膚、歯ぐきからの出血が起こりやすい。
肝疾患(肝硬変など):血液を固める働きが低下し、鼻血や消化管出血を起こしやすい。
血液の病気(白血病・血小板減少症など):血が固まりにくくなり、出血が長引く。 - 口腔・歯茎からの出血
歯周病・歯肉炎:高齢者は歯茎が弱くなり、歯磨きの際に出血しやすい。
義歯(入れ歯)の刺激:合わない入れ歯が口内を傷つけることがある。 - 鼻血(鼻粘膜の乾燥・刺激)
・冬場やエアコンの影響で粘膜が乾燥し、出血しやすくなる。
・鼻を強くかむ・いじる等でも 高齢者は鼻血が出やすいことがある。 - 消化管からの出血
・胃潰瘍・十二指腸潰瘍:ストレスやピロリ菌の影響で、胃や腸の粘膜が傷つき出血することがある(吐血・黒色便)。
・大腸がん・ポリープ: 便に血が混じることがある。
・痔(いぼ痔・切れ痔): 排便時に肛門から出血することがある。
出血したらどうなる?<例と対処法>
高齢者にとって「出血」は、単なる軽傷では済まされないこともあります。
若い頃ならすぐに止まるような出血でも、高齢になると 血が止まりにくくなったり、傷が治りにくくなったり するため、注意が必要です。
高齢者が出血した場合に起こりうる影響と、適切な対応について解説します。
基本的には、介護者は応急処置をした後は、在任の看護師に連絡して指示を仰ごう!
1. 出血が止まりにくくなる
高齢者は、加齢による 血管のもろさ や 血液の凝固能力の低下 により、出血が止まりにくいことがあります。
特に、抗凝固薬(ワルファリン、アスピリンなど)を服用している人は、ちょっとした傷でも長時間血が止まらないことがあるため要注意です。
<例>
- 転倒して膝を擦りむいたが、なかなか血が止まらない
- 鼻血が出たが、10分以上止まらず貧血気味になった
<対処法>
- 圧迫止血(清潔なガーゼや布で強く押さえる)をする
- 10~15分経っても止まらない場合は医療機関を受診
2. 感染症のリスクが高まる
高齢者の皮膚は薄く、免疫力も低下しているため、傷口から 細菌感染 を起こしやすいです。小さな切り傷や擦り傷が、思わぬ 化膿や炎症 を引き起こすこともあります。
<例>
- ささくれを引っ張ったら出血し、翌日赤く腫れて膿んできた
- 転倒してできた傷がなかなか治らず、周囲が赤く腫れてきた
<対処法>
- すぐに水や消毒液で洗い、清潔なガーゼで保護
- 赤み・腫れ・熱を持つなどの症状が出たら、早めに病院へ
3. 大量出血によるショックの危険性
高齢者は、貧血や低血圧 を起こしやすいため、大量出血すると急激に体調が悪化し、意識を失うこともあります。
特に 脳出血や消化管出血 など、体内で起こる出血(内出血)は見た目では分かりにくいため、注意が必要です。
<例>
- 便が黒くなった(胃腸からの出血の可能性)
- 頭をぶつけた後、意識がもうろうとしている(脳出血の可能性)
<対処法>
- 出血量が多い場合はすぐに救急車を呼ぶ(119番)
- 便の色が黒くなったり、吐血があったりしたら消化器科を受診
4. 出血による貧血・体力低下
高齢者は 血液を作る能力 も低下しているため、慢性的な出血が続くと 貧血 になりやすくなります。貧血が進むと ふらつきや息切れ、動悸 などが起こり、転倒のリスクも高まります。
<例>
- 歯ぐきからの出血が続いていて、最近めまいが増えた
- 痔からの出血が長期間続いており、疲れやすくなった
<対処法>
- 出血が続く場合は、放置せずに病院を受診
- 鉄分を意識した食事(レバー、ほうれん草、赤身肉など)をとる
出血した後のリスクマネジメント
まずは大事なポイントは
- 感染リスクを意識し、健康管理と周知を徹底すること
- 記録を具体的にわかりやすく書くこと
・出血の量や部位
・何が原因で出血したのか(転倒、皮膚損傷など)
・ 事故発生時の時間、場所、対応した職員の名前を明記
事故原因を徹底分析
- 転倒・衝突による出血:施設内の危険箇所をチェックし、環境整備
- 皮膚の脆弱性による出血:利用者の健康状態を考慮したケアの見直し
- 支援中の出血:支援技術やルールの確認と改善・向上
職員間での情報共有と研修の実施
- 事故後に カンファレンス(事例検討会) を開き、対応を振り返る
- 転倒予防、スキンケア、感染予防 など、事故防止に向けた職員研修を定期的に行う
施設の環境改善
- 床の滑り止め対策や、ベッド・椅子の高さ調整
- 夜間の見守り強化(特に夜間トイレ移動時の転倒対策)
- 利用者の 服薬管理と把握(抗凝固薬を服用している利用者のリスク把握)
まとめ
若い頃なら大したことのない出血でも、高齢者にとっては 長引いたり、合併症を招いたりする 可能性があります。出血がなかなか止まらない、頻繁に出血する場合は 主治医や医療機関に相談 することが重要です。

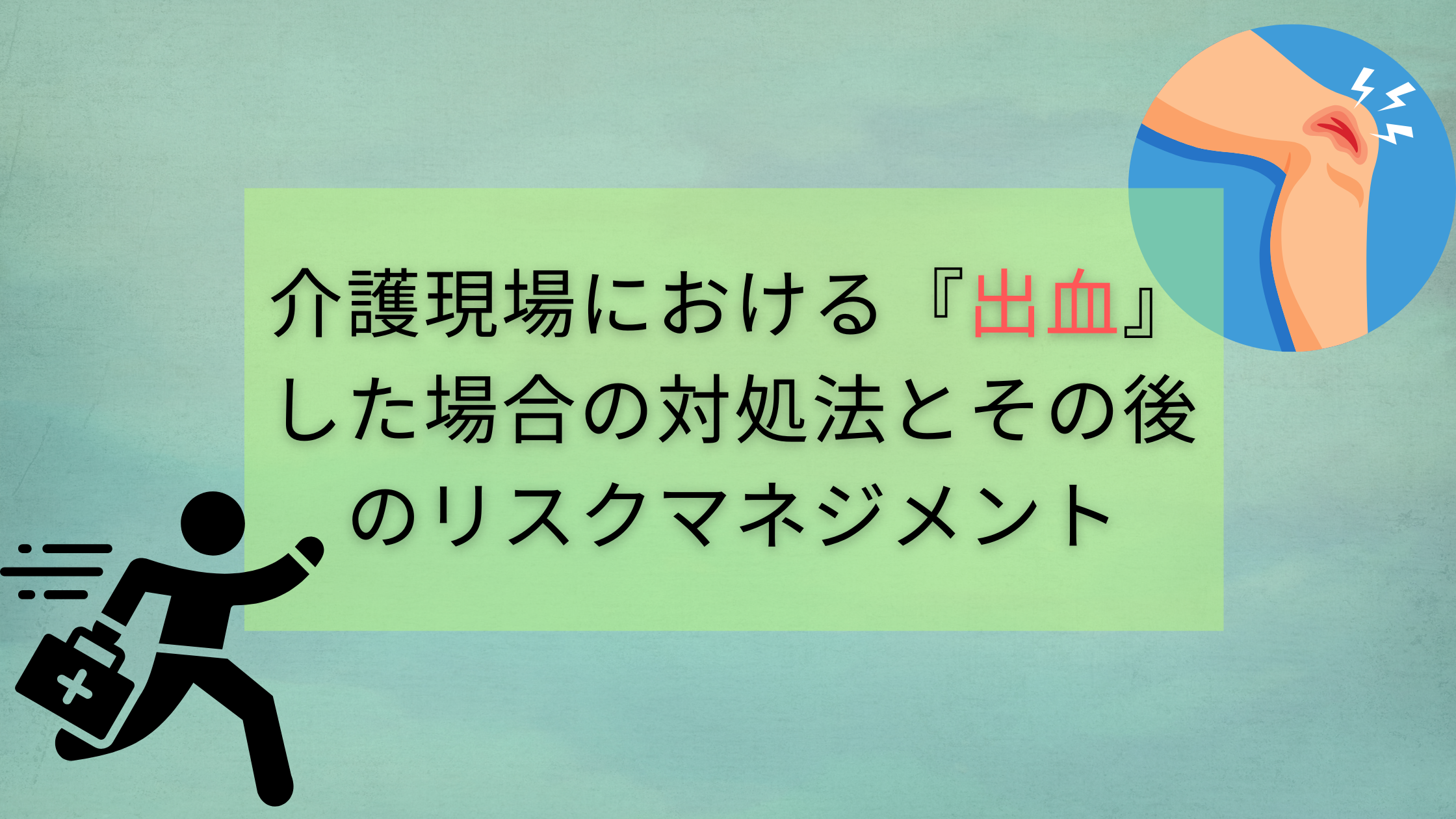
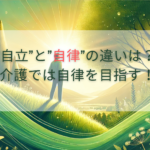
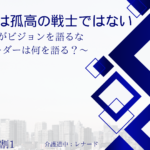



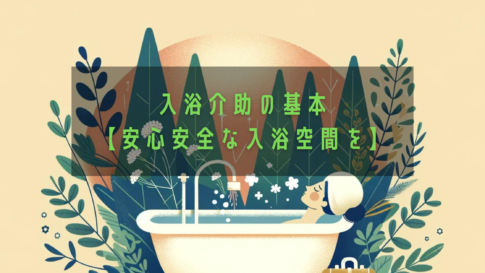


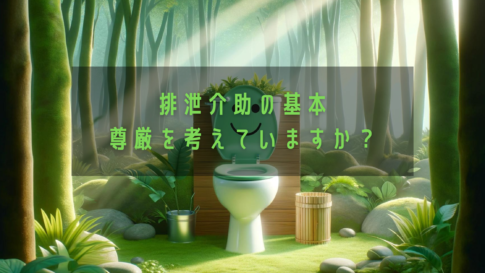



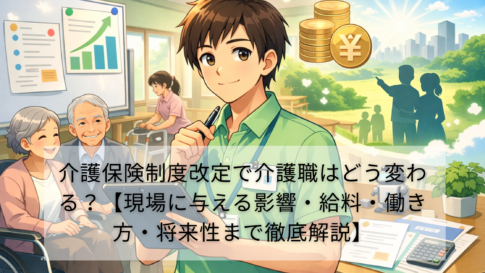
コメントを残す